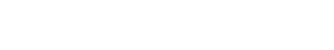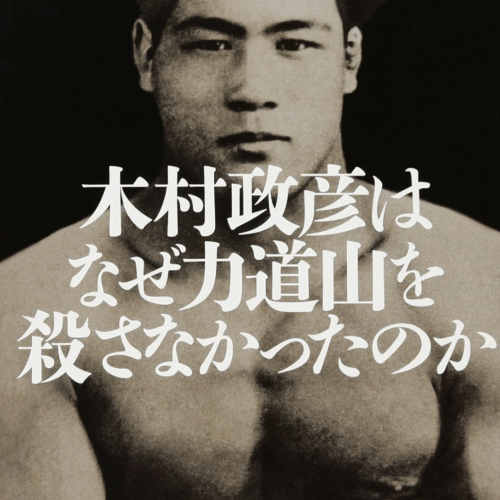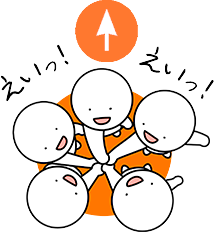2025年8月18日
その”常識”、本当に常識? ~階段を飛ぶマグロと氷上の鉄拳から学んだ「当たり前」の作り方~
314 views
皆さん、こんにちは!
マーケティング2課の池田です。寝ても覚めてもマーケティングのことばかり考えている
僕ですが、今日はちょっと変わった「原体験」についてお話しさせてください。
テーマは「当たり前の恐ろしさと、面白さ」について。
少しだけショッキングに聞こえるかもしれませんが、あくまで僕個人の体験談として、
ユーモアと共にお届けできればと思います!
第一章:入部届より先に、バリカンと謝罪
僕が「当たり前」というものの不思議な力に気づいたのは、中学校の部活動でした。
希望に胸を膨らませ、アイスホッケー部の門を叩いた入学1週間後。
僕を待っていたのはスティックではなく、バリカンでした。
「俺に挨拶もなしに入部だと? 全員、職員室に来い!」
顧問の先生の一声で、新入部員は全員職員室へ。
深々と頭を下げ、入部を許可してもらうための条件は、なんと「全員、丸坊主になること」。
桜がまだ咲き誇る4月に、突如として校内に丸坊主の一団が生まれたのです。
他の生徒からすれば、ちょっとした事件だったかもしれません(笑)。
こうして始まった部活生活。しかし、本当の衝撃はここからでした。
最初の1週間、過酷なトレーニングで、部屋までいくこともできずしばらく
玄関で寝る生活でした。
毎日10キロ走、地獄のようなインターバル走。
雨が降って「やった!外周がない!」と喜んだ日には、
校舎の1階から6階までの階段往復2時間コースが待っていました。
その中で、今でも忘れられない光景があります。
汗と熱気で濡れた階段は、まさにスケートリンク。
こで、多くの先輩たちがツルッと足を滑らせ、
まるで水揚げされたマグロのように階段を滑り落ちていくのです。
本当にアニメみたいに「ビューン!」と音を立てて。もちろん、普通に怪我をする人もいました。
今思えば「練習を止めろ!」という話ですが、
当時は誰もが「また誰か飛んでるな」くらいにしか思っていませんでした。
それが、僕たちの「当たり前」だったのです。
トレーニングの締めは、グラウンド裏での2時間にも及ぶ正座。
そして、そこで待っているのは先輩たちによる「愛の指導」でした。
理不尽な理由でビンタや蹴りが飛んでくることも日常。
歪んだ縦社会の「当たり前」がそこにはありました。
第二章:氷上の王様と、”病院送り”という指令
「そんな中学校生活ならもう勘弁」と思いますよね。
その環境が変わると喜び進学した高校でしたが、
そこではまた別の厳しさが待ち構えていたのです。
監督は元プロ選手。チームは、彼の王国でした。
その中で僕の心を最も蝕んだ「当たり前」。
それは、試合の結果が見え始めた時に、
監督から発せられる「相手チームのエースを病院送りにせよ」という指令でした。
数年前に世間を騒がせた大学アメフト部の悪質タックル問題がありましたが、僕たちの世界では、それが「作戦」の一つとして普通に行われていたのです。
日大タックル映像▼
もちろん、心の中では「おかしい」「やりたくない」という葛藤がありました。
日大タックル映像しかし、チームで勝つため、監督に認められるため、
そして何より、その環境で生き残るためには、
その指令こそが「正義」であり「当たり前」でした。
逆らう選択肢など、当時の僕にはありませんでした。
なぜ、監督はそんな非道な指示を「当たり前」のように出せたのだろうか。
今になって、こう考えます。
僕たちの監督は、今ほど海外挑戦が当たり前ではなかった時代に、
単身ロシアという地に飛び込んで選手として活躍していた人でした。
日本人への風当たりの強さ、氷上での仕打ちは、
きっと僕たちの想像を絶するものだったのだと思います。
まさに「殺すか、殺されるか」の世界で戦ってきたのでしょう。
監督にとっては、相手のエースを潰すことなど、
生き残るための「当たり前の戦術」の一つだったのかもしれません。
監督自身もまた、壮絶な環境の中で形成された「当たり前」の体現者だったのです。
(※だからといって、決して許されることではありません!
そして、アイスホッケー自体は、本当に素晴らしいスポーツなんです!ぜひこの動画を…(以下略))
最高なので絶対みてね
第三章:「当たり前」の正体
さて、ここまで僕の壮絶(?)な体験談をお話ししましたが、皆さん、どう思いましたか?
「やばすぎるだろ」「ありえない」と思った方も多いのではないでしょうか。
しかし、最も怖いのは、当時の僕はその環境を『普通』だと思っていたということです。
もちろん、辛い、辞めたいと思う瞬間はありました。
でも、プロを目指すなら、強くなるためには、
これが「当たり前」なのだと、疑うことすら忘れていました。
「当たり前」が一度形成されると、僕たちはそれを無条件に受け入れてしまうのです。
最近読んだ本に、「当たり前」が組織に浸透していくロジックについて書かれていました。
それと宗教構造が混ざりあい最強の状態が出来上がっていたと今思えば感じます
マーケの方は必読書だと思うので興味のある方はぜひ
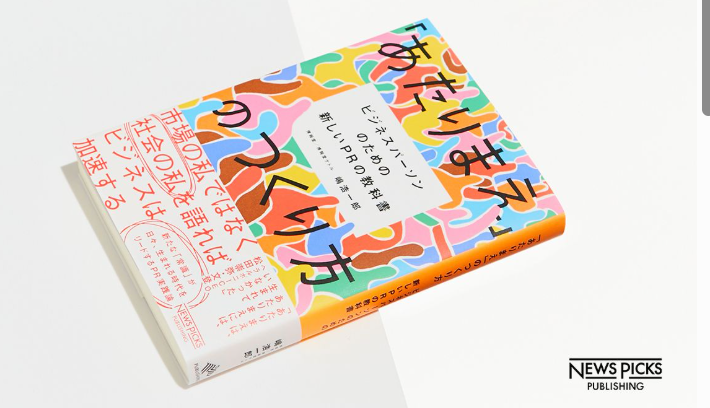
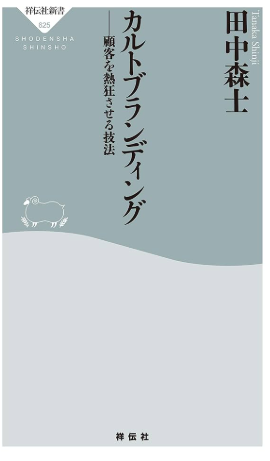
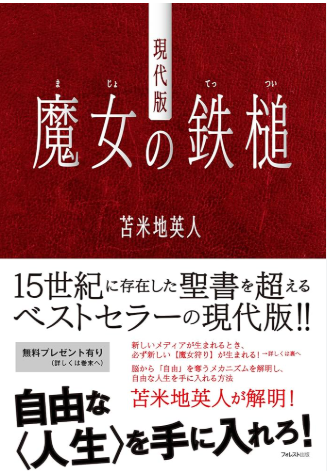
最終章:今の僕たちの「当たり前」は?
これが、プロの選手を目指して戦ってきた僕の「当たり前」でした。
では、皆さんの「当たり前」は何でしょうか?
今の社会にも、こういった見えない「当たり前」が、
知らず知らずのうちに根付いているのかもしれません。
それ自体に良い悪いはありません。
しかし、大事なのは一度立ち止まって「これって、本当に今もベストな方法なのかな?」
「他の人にとっては、当たり前じゃないかもしれない」と考えてみること。
僕の過去の体験は極端な例ですが、そこから学んだのは、
自分の常識を疑う視点を持つことの大切さです。
自分の「当たり前」が、他の人には「当たり前」ではない。
その違いに気づき、尊重すること。
そのギャップを知ることこそが、新しい価値観を生み出し、
より良い社会を築いていくための、最高のヒントになるのではないかと僕は信じています。
この記事が、皆さんの持つ「当たり前」という名のバイアスを、
少しだけ解除するきっかけになれば良いなと思い書かせていただきました!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!